年末年始の放送大学
2020.12.27
以前も紹介した放送大学ですが、12月29日~1月4日が年末・年始特別編成になっています。
今年の正月は自宅で過ごす人が多いと思いますが、半日からせいぜい3日間くらいで一気に見られるような編成の番組が多数ありますので、この機会に視聴してみてはいかがでしょうか。私のおすすめは「ダイナミックな地球」と「アジアと漢字文化」ですが、12月31日午前9時からは「大学入試をどう考えるのか」なんていう講義も放送されます。
もちろん、面白いと感じる番組ばかりだという保証はありません。というより、全部の授業が面白い大学なんてこの世に存在しません。興味を持てる内容は人によっても違うでしょう。しかし、たとえばつまらないと感じる授業を視聴したとして、それをつまらないと判断できたことはちゃんと自分の経験になります。またシリーズものの番組であっても、見たいものだけつまみ食いで見てまったく問題ありません。
詳しい放送予定は週間番組表をご覧ください。
今年の正月は自宅で過ごす人が多いと思いますが、半日からせいぜい3日間くらいで一気に見られるような編成の番組が多数ありますので、この機会に視聴してみてはいかがでしょうか。私のおすすめは「ダイナミックな地球」と「アジアと漢字文化」ですが、12月31日午前9時からは「大学入試をどう考えるのか」なんていう講義も放送されます。
もちろん、面白いと感じる番組ばかりだという保証はありません。というより、全部の授業が面白い大学なんてこの世に存在しません。興味を持てる内容は人によっても違うでしょう。しかし、たとえばつまらないと感じる授業を視聴したとして、それをつまらないと判断できたことはちゃんと自分の経験になります。またシリーズものの番組であっても、見たいものだけつまみ食いで見てまったく問題ありません。
詳しい放送予定は週間番組表をご覧ください。
日本人の英語シリーズ
2020.12.13
左から、日本人の英語(ISBN 4-00-430018-5)、続 日本人の英語(ISBN 4-00-430139-4)、実践 日本人の英語(ISBN 978-4-00-431420-2)


英語を専攻した日本人にとっては耳の痛い話ばかりが詰まった三部作です。
最初の本は「日本人の英語が奇妙なのは、ここに誤解があるからじゃないの」という指摘、2冊目は「書くのが苦手なのはたしかにそうだけど、そもそも読めてないんじゃないの」という考察、3冊目は「こう書くよりもこう書く方が、しっかりした英語になるよ」というレッスンを中心にしています。とくに1冊めは高校生では読めないというほど難しい本ではありませんが、受験英語に直結する内容でもないので、むりに急いで読むことはないかなと思います。
この本を読むと、日本人が英語を書くのがどれほど難しいか改めて実感できますし、間違いを探して修正できる作文と違い話すときには、いったいどれほどのデタラメを言っているか想像するのも嫌になりますが、そこで恐れをなしては本末転倒です。私の意見では、外国語である以上少しくらい間違えるのは当然のことで、間違えないようにしようと思ったとたん語学を学ぶのは不可能になります。これはまなびやの授業でもことあるごとに指摘している鉄則で、突き詰めれば、日本人が日本語で読み書きや会話をするときだって、常に100点満点の日本語を使っているわけではありません。ただ慣れているから間違っても気にならないだけなのです。
そうすると、前回紹介したような本物の達人を最終的には目指すのであっても、そのレベルに達するまではどんどん間違えて、間違えすぎて間違いに鈍感になって、間違いに気付いてもまだまだ間違えて、ということを繰り返す以外に、どうにもしようがないわけです。またその達人でさえも、ネイティブと同程度しか間違えないというだけで、まったく間違えないのでは決してありません。もしそのことに気付くことができたら、英語だけでなくあらゆる勉強や練習に応用できる、貴重な体験になります。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ


英語を専攻した日本人にとっては耳の痛い話ばかりが詰まった三部作です。
最初の本は「日本人の英語が奇妙なのは、ここに誤解があるからじゃないの」という指摘、2冊目は「書くのが苦手なのはたしかにそうだけど、そもそも読めてないんじゃないの」という考察、3冊目は「こう書くよりもこう書く方が、しっかりした英語になるよ」というレッスンを中心にしています。とくに1冊めは高校生では読めないというほど難しい本ではありませんが、受験英語に直結する内容でもないので、むりに急いで読むことはないかなと思います。
この本を読むと、日本人が英語を書くのがどれほど難しいか改めて実感できますし、間違いを探して修正できる作文と違い話すときには、いったいどれほどのデタラメを言っているか想像するのも嫌になりますが、そこで恐れをなしては本末転倒です。私の意見では、外国語である以上少しくらい間違えるのは当然のことで、間違えないようにしようと思ったとたん語学を学ぶのは不可能になります。これはまなびやの授業でもことあるごとに指摘している鉄則で、突き詰めれば、日本人が日本語で読み書きや会話をするときだって、常に100点満点の日本語を使っているわけではありません。ただ慣れているから間違っても気にならないだけなのです。
そうすると、前回紹介したような本物の達人を最終的には目指すのであっても、そのレベルに達するまではどんどん間違えて、間違えすぎて間違いに鈍感になって、間違いに気付いてもまだまだ間違えて、ということを繰り返す以外に、どうにもしようがないわけです。またその達人でさえも、ネイティブと同程度しか間違えないというだけで、まったく間違えないのでは決してありません。もしそのことに気付くことができたら、英語だけでなくあらゆる勉強や練習に応用できる、貴重な体験になります。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ
読む辞典
2020.12.13
左から、英語類義語活用辞典(ISBN 4-480-08756-7)、日英語表現辞典(ISBN 4-480-08807-5)


これは凄い本です。編著者は「戦後日本最初の英文コラムニスト」で、しかもその仕事を26年間続けたというのですから、まるで想像もつかないほどの英語の達人です。そのノウハウの一部が、読み物としても十分楽しめる体裁でまとめられています。
この本を手に取って欲しいのは、他の誰よりもまず「自分は英語が得意だ」とか「英語の勉強が好きだ」と思った高校生です。何年生でも構いませんから、そう思ったらすぐにでも、この本を読んでみるべきです。中学生には少し難しいかもしれませんが、中身を眺めてみて大変そうなら「いつか読んでみよう」と後回ししてもよいでしょう。野球が好きな中高校生もサッカーが得意な中高校生も、美術が好きな中高校生も楽器が得意な中高校生も、その分野の「スター」をすでに知っています。あなただけが知らずにいるのは大損です。
英文科に進んだ大学生には、いいから買うだけ買って手元に置いておきなさいと、強く勧めます。決して損はしません。もしこの記事の読者が大人で、知り合いに英文科へ進む生徒がいたら、ぜひ入学祝に贈ってあげてください。2冊や3冊ダブって持っていてもまったく差し支えない本です。英文科でない文学部の生徒も、手には取ってみて欲しいと思います。
もちろん、タイトルにある通り辞典としても使えます。類義語辞典は1979年、表現辞典は1980年の初版ですが、単語の用法は古くなっても言葉の理解自体は古くなりません。大人の読み物あるいは教養書として、英作文のアンチョコとして、読書のお供に、きっと活躍してくれるでしょう。
なお、日本人が英語を書くのがどれだけ難しいか、という話題には次の記事で触れます。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ


これは凄い本です。編著者は「戦後日本最初の英文コラムニスト」で、しかもその仕事を26年間続けたというのですから、まるで想像もつかないほどの英語の達人です。そのノウハウの一部が、読み物としても十分楽しめる体裁でまとめられています。
この本を手に取って欲しいのは、他の誰よりもまず「自分は英語が得意だ」とか「英語の勉強が好きだ」と思った高校生です。何年生でも構いませんから、そう思ったらすぐにでも、この本を読んでみるべきです。中学生には少し難しいかもしれませんが、中身を眺めてみて大変そうなら「いつか読んでみよう」と後回ししてもよいでしょう。野球が好きな中高校生もサッカーが得意な中高校生も、美術が好きな中高校生も楽器が得意な中高校生も、その分野の「スター」をすでに知っています。あなただけが知らずにいるのは大損です。
英文科に進んだ大学生には、いいから買うだけ買って手元に置いておきなさいと、強く勧めます。決して損はしません。もしこの記事の読者が大人で、知り合いに英文科へ進む生徒がいたら、ぜひ入学祝に贈ってあげてください。2冊や3冊ダブって持っていてもまったく差し支えない本です。英文科でない文学部の生徒も、手には取ってみて欲しいと思います。
もちろん、タイトルにある通り辞典としても使えます。類義語辞典は1979年、表現辞典は1980年の初版ですが、単語の用法は古くなっても言葉の理解自体は古くなりません。大人の読み物あるいは教養書として、英作文のアンチョコとして、読書のお供に、きっと活躍してくれるでしょう。
なお、日本人が英語を書くのがどれだけ難しいか、という話題には次の記事で触れます。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ
英文法の本
2020.12.13
英文法の「なぜ」(ISBN 978-4-469-24623-0)

これは「文法を覚えさせる」ための本ではなく、どうしてそういう仕組みになったのかを、歴史を紹介しながら解説してくれる、なかなか画期的な本です。書いてある内容は平易で、しっかり勉強していれば高校入学前の春休みくらいに読んでも理解できる生徒はいるだろうと思います。
言葉を勉強するということは、歴史や習慣や感じ方や考え方を勉強するということ、まとめていえば文化を勉強するということであって、それらを無視して機械的な反復練習だけに頼るのは、無駄に遠回りな道になります。とすると英語の成り立ちについての説明は英語教育の中で普通に行われているはずですが、この本が画期的なのは、現代英語を勉強する上で頭を悩ませるだろう問題をずらりと解説しているところです。また従来、大学で教わる英語の歴史は、たいてい「英語の歴史を理解するための」ものであって、中高生のとき悩んだであろう疑問を解決するためのものでないのが普通でした。
ただこの本が大学受験の英語に役立つかというと、話がスッキリした状態で勉強を進められるメリットはあるものの、直接的なご利益はそう多く期待できないかもしれません。そういう意味では、受験が終わった春休みのちょっと空いた時間に読むとか、英語を勉強し直したい大人が手始めに読んでみる、といった使い方の方が適しているかもしれません。文学部に入学する生徒でなくても、自分が勉強したことの後ろにどういう歴史の繋がりがあったのか、その手ががりにだけでも触れておくのは決して損になりません。読み物としても十分に楽しめる本です。
考える英文法(ISBN 978-4-480-09910-5)
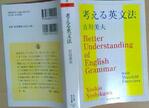
今度は正真正銘「英文法の勉強の本」です。1966年に出版された本の復刻版で、冒頭「はしがき」によると対象読者は「高等学校二三年生以上」となっており、ようするに高校の英文法を一通り学んだ後に知識を整理するための本です。
たしかにこの本はあらゆるところが古く、次から次と波のように押し寄せる教え方も古ければ、擬似関係詞だの代不定詞だのヨクワカラナイ用語が出でもきますし、出版から50年以上経ち英語が変化してしまった部分もあります。しかしそれでも、例文を厳選し、丁寧かつ簡潔に説明しながら、実際の試験問題まで盛り込んで、これだけの範囲をカバーしてあることには、一定の意義があります。少なくとも、ただ解いては答え合わせを繰り返すタイプの「文法ワーク」よりも、はるかに効果的でしょう。これも、以前紹介した単語帳のDUO selectと同様「どうせやるならこれがいいんじゃないか」というものです。
なお、この本はまなびやの分類では「教材」扱いでないため、貸出の対象になります。あくまで「読む」ための貸出なので、問題集として本格的に「解きたい」人は自分で購入してください。
<英文法>を考える(ISBN 978-4-480-08230-5)
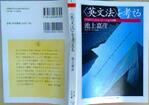
タイトルに「英文法」とありますが、これはある種の「レトリック」で、1999年出版当時の「最近の言語学」が諸問題をどう扱っているかについて、英語を例に取りながら紹介する本です。そのため、高校生が英語の試験勉強のためにこの本を読んでも、ほとんど効果は期待できません。そういうわけで、万人にお薦めする本ではありませんが、文学部に進んだ大学生なら、言語学を学ぶ機会が乏しい専攻であればなおさら、手に取ってみる価値はあるでしょう。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ

これは「文法を覚えさせる」ための本ではなく、どうしてそういう仕組みになったのかを、歴史を紹介しながら解説してくれる、なかなか画期的な本です。書いてある内容は平易で、しっかり勉強していれば高校入学前の春休みくらいに読んでも理解できる生徒はいるだろうと思います。
言葉を勉強するということは、歴史や習慣や感じ方や考え方を勉強するということ、まとめていえば文化を勉強するということであって、それらを無視して機械的な反復練習だけに頼るのは、無駄に遠回りな道になります。とすると英語の成り立ちについての説明は英語教育の中で普通に行われているはずですが、この本が画期的なのは、現代英語を勉強する上で頭を悩ませるだろう問題をずらりと解説しているところです。また従来、大学で教わる英語の歴史は、たいてい「英語の歴史を理解するための」ものであって、中高生のとき悩んだであろう疑問を解決するためのものでないのが普通でした。
ただこの本が大学受験の英語に役立つかというと、話がスッキリした状態で勉強を進められるメリットはあるものの、直接的なご利益はそう多く期待できないかもしれません。そういう意味では、受験が終わった春休みのちょっと空いた時間に読むとか、英語を勉強し直したい大人が手始めに読んでみる、といった使い方の方が適しているかもしれません。文学部に入学する生徒でなくても、自分が勉強したことの後ろにどういう歴史の繋がりがあったのか、その手ががりにだけでも触れておくのは決して損になりません。読み物としても十分に楽しめる本です。
考える英文法(ISBN 978-4-480-09910-5)
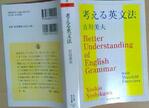
今度は正真正銘「英文法の勉強の本」です。1966年に出版された本の復刻版で、冒頭「はしがき」によると対象読者は「高等学校二三年生以上」となっており、ようするに高校の英文法を一通り学んだ後に知識を整理するための本です。
たしかにこの本はあらゆるところが古く、次から次と波のように押し寄せる教え方も古ければ、擬似関係詞だの代不定詞だのヨクワカラナイ用語が出でもきますし、出版から50年以上経ち英語が変化してしまった部分もあります。しかしそれでも、例文を厳選し、丁寧かつ簡潔に説明しながら、実際の試験問題まで盛り込んで、これだけの範囲をカバーしてあることには、一定の意義があります。少なくとも、ただ解いては答え合わせを繰り返すタイプの「文法ワーク」よりも、はるかに効果的でしょう。これも、以前紹介した単語帳のDUO selectと同様「どうせやるならこれがいいんじゃないか」というものです。
なお、この本はまなびやの分類では「教材」扱いでないため、貸出の対象になります。あくまで「読む」ための貸出なので、問題集として本格的に「解きたい」人は自分で購入してください。
<英文法>を考える(ISBN 978-4-480-08230-5)
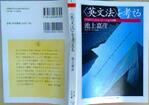
タイトルに「英文法」とありますが、これはある種の「レトリック」で、1999年出版当時の「最近の言語学」が諸問題をどう扱っているかについて、英語を例に取りながら紹介する本です。そのため、高校生が英語の試験勉強のためにこの本を読んでも、ほとんど効果は期待できません。そういうわけで、万人にお薦めする本ではありませんが、文学部に進んだ大学生なら、言語学を学ぶ機会が乏しい専攻であればなおさら、手に取ってみる価値はあるでしょう。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ
受験術の本
2020.11.30
数学受験術指南(ISBN 978-4-12-205689-3)

最初に断っておきたいのですが、これは古い本で、1981年に出版された本の文庫版です。書かれたのは著者の言う「ガンバリズム」の全盛期で、著者自身が経験した「受験」も今とはまったく異なるものだったことは、気に留めておかなければなりません。とくに第1章は、当時の受験教育の様子を知らない人には何を言っているのかわかりにくいでしょう。
しかしそこさえ差し引いておけば、第2章以降は、これから受験をする人にも、かつて受験をした人にも、面白い読み物になってくれます。全体としては「わからないことがないように準備する」「ガンバリ」は効率が悪いから「わからないことに対して理屈の通った答えが出せる」「ウマイコト」を目指してみようという論調で、採点の現場を経験したからこその裏話や、著者自身の受験体験、自分の専門分野である数学の宣伝など、寄り道もバランスよく交えながら、一気に読める程度の分量で書かれています。
京都大学の教授が書いた本、と聞くと難しそうな印象を持つかもしれませんが、小難しいことは書いてありません。巻末のほうに、著者が「毎日中学生新聞」に寄稿したというコラムがいくつか転載されており、文章の難しさは本編と似たようなものです。初めてこの本を読む人は、217ページの「解説」から読み始めると、面食らうことなく楽しめるでしょう。
キミは何のために勉強するのか 試験勉強という名の知的冒険2 (ISBN 978-4-479-19052-3)

タイトルの酷さが壮絶すぎて、思わずフルタイトルで掲載してしまいました。以前書いたように、私は本棚に本を並べるのを趣味にしているのですが、生まれて初めて「ブックカバー」なるものを買ってしまおうかと本気で考えました。
私の個人的な思いはさておき、これは「教える科目や学年に関わらず、先生になりたい人」にぜひ読んで欲しい本です。受験生の親の読み物としても、多少の読みにくさを克服できるなら面白い本ですが、子供にこれを「読ませよう」とはしない方が無難です。タイトルに「2」とついているからには「1」も出ており、まなびやの蔵書にも入っていますが、こちらは「2」が気に入った人だけ手に取ってみればいいかなと思います。
この本が言っているのはようするに「高校までの勉強でちゃんと『 抽象性』を身に付けておいてよ、でないと浪人してからの1年間じゃどうにもできないよ」(かなり悪意のある意訳)という訴えと、その抽象性を身に付けるための方法論、あとは「自己不信は恐ろしいよ」とか「むやみに可能性の幅を狭めるのは損だよ」といった忠告です。初版の2012年から8年経ち、受験生が抽象性を扱う能力は低迷の一途を辿っていますから、私を含め「子供に教える」立場の者なら一度は考えてみるべき内容です。
最後に、この本を手に取った、あるいはタイトルだけ見て手に取らなかった受験生に言っておきたいのですが、著者は予備校の英語の先生として最優秀の人です。私も浪人したときに1年間受講し、ちゃんと成績も伸びました。そのことは言い添えておきたいと思います。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ

最初に断っておきたいのですが、これは古い本で、1981年に出版された本の文庫版です。書かれたのは著者の言う「ガンバリズム」の全盛期で、著者自身が経験した「受験」も今とはまったく異なるものだったことは、気に留めておかなければなりません。とくに第1章は、当時の受験教育の様子を知らない人には何を言っているのかわかりにくいでしょう。
しかしそこさえ差し引いておけば、第2章以降は、これから受験をする人にも、かつて受験をした人にも、面白い読み物になってくれます。全体としては「わからないことがないように準備する」「ガンバリ」は効率が悪いから「わからないことに対して理屈の通った答えが出せる」「ウマイコト」を目指してみようという論調で、採点の現場を経験したからこその裏話や、著者自身の受験体験、自分の専門分野である数学の宣伝など、寄り道もバランスよく交えながら、一気に読める程度の分量で書かれています。
京都大学の教授が書いた本、と聞くと難しそうな印象を持つかもしれませんが、小難しいことは書いてありません。巻末のほうに、著者が「毎日中学生新聞」に寄稿したというコラムがいくつか転載されており、文章の難しさは本編と似たようなものです。初めてこの本を読む人は、217ページの「解説」から読み始めると、面食らうことなく楽しめるでしょう。
キミは何のために勉強するのか 試験勉強という名の知的冒険2 (ISBN 978-4-479-19052-3)

タイトルの酷さが壮絶すぎて、思わずフルタイトルで掲載してしまいました。以前書いたように、私は本棚に本を並べるのを趣味にしているのですが、生まれて初めて「ブックカバー」なるものを買ってしまおうかと本気で考えました。
私の個人的な思いはさておき、これは「教える科目や学年に関わらず、先生になりたい人」にぜひ読んで欲しい本です。受験生の親の読み物としても、多少の読みにくさを克服できるなら面白い本ですが、子供にこれを「読ませよう」とはしない方が無難です。タイトルに「2」とついているからには「1」も出ており、まなびやの蔵書にも入っていますが、こちらは「2」が気に入った人だけ手に取ってみればいいかなと思います。
この本が言っているのはようするに「高校までの勉強でちゃんと『 抽象性』を身に付けておいてよ、でないと浪人してからの1年間じゃどうにもできないよ」(かなり悪意のある意訳)という訴えと、その抽象性を身に付けるための方法論、あとは「自己不信は恐ろしいよ」とか「むやみに可能性の幅を狭めるのは損だよ」といった忠告です。初版の2012年から8年経ち、受験生が抽象性を扱う能力は低迷の一途を辿っていますから、私を含め「子供に教える」立場の者なら一度は考えてみるべき内容です。
最後に、この本を手に取った、あるいはタイトルだけ見て手に取らなかった受験生に言っておきたいのですが、著者は予備校の英語の先生として最優秀の人です。私も浪人したときに1年間受講し、ちゃんと成績も伸びました。そのことは言い添えておきたいと思います。
-関連記事-
図書貸出のお知らせ
 2020.12.27 13:12
|
2020.12.27 13:12
| 

